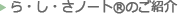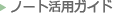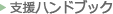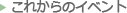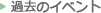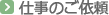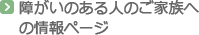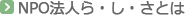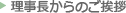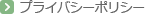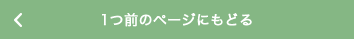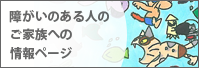イベント情報
イベントレポート
2025/3/26【東京】元気に体操~心身の健康につなげる準備体操と備え~(3月ら・し・さサロン)
日頃から生涯現役で健康に暮らすためには心身の健康が非常に重要であると感じており、
今回の「ら・し・さサロン」の受講を楽しみにしておりました。
初めての参加ということもあり、少し緊張しながら会場に入りましたが、
明るく広々とした教室で、笑顔のスタッフの方々に温かく迎えられ、
リラックスして参加することができました。
講師は、医療法人瑞穂会で介護予防認定理学療法士としてご活躍中の、阿久澤直樹先生です。
阿久澤先生は、健康づくりや認知症予防教室、
転倒防止・骨折予防、安全な生活などの地域支援に力を入れていらっしゃり、
その豊富なご経験をもとに、
前半では「健康を守るために必要な知識」を学び、
後半では座位でできる準備体操を実践しながら教えていただきました。
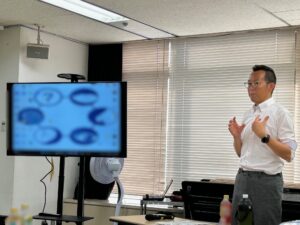
講義のポイントは、「からだ と こころ と周りの人との関わり」となり、
WHO憲章による
「健康とは、病気でないとか、弱っていないということではなく、
肉体的にも、精神的にも、そして社会的にも、
すべてが満たされた状態であることをいう」
という定義についてもご紹介いただきました。
日本人の平均寿命は年々伸びており、
加齢に伴ってさまざまな機能が低下するのは自然なことです。
しかし、認知症の診断基準やフレイル対策を知ることで、
日々の生活をより安全に過ごすための方法がわかりました。
認知機能の衰えに関して、教えていただいた
「経験と記憶を生かして、先を読んで行動することができない」
「相手の気持ちや周りの空気を察して、行動を決めることができない」
「湧きおこる感情を抑えられない、素直な反応を示す」
「注意・集中力が不十分、同時にたくさんのことを処理できない」
「複雑な計算、文章読解、潜在的なものを掘り下げて探求できない」
「忘れ物が多い、覚えてられない」
などの項目には、同居している92歳の母に当てはまることが多くありました。
認知機能が衰えていく中でも感じる能力は衰えないため、
「さっき言ったじゃない!」などと強く言われると、
母がショックを受けることがあると伺い、
自分の言動について改めなければと反省しました。
また、時代の流れの中で高齢者の生活では友人が減り、
話す機会も少なくなっているという統計結果がありました。
人生100年時代を迎える中で、
ひとり暮らしの高齢者が増加している傾向も見受けられます。
社会とのつながりを失うことがフレイルの始まりとなるのであれば、
人との交流や会話の機会を持つことが非常に重要です。
だからこそ、個人で頑張るのではなく、地域で共に支え合い、
助け合う仲間を増やすことが大切だと強く感じました。
運動習慣についてお話しされていた内容は、
運動に苦手意識を持つ人もいるが、運動を「活動」と捉えることで、
日常の散歩や掃除も立派な運動の一部であるということでした。
脳、神経、筋肉は密接に繋がっており、
使われていない筋肉を自分で動かすことによって運動能力を維持でき、
いざという時の動作に備えることができるという点も強調されていました。
運動(活動)の準備運動として実践したのは、座位での足踏み、
尻踏み、背伸び、肩まわし、ヨガなどで、
これらを行うことで歩き出しの転倒やよろめきを防ぐことができると実感しました。
さらにあまり使っていない筋肉を動かすことによる気持ち良さを感じることもできました。
最後の質問タイムでは、お茶とお菓子が配られ、
和やかな雰囲気の中で、ひとつひとつの質問に丁寧に解説いただきました。

大変楽しく、充実した時間を共に過ごさせていただき、
ありがとうございました。
山岡正子 (終活アドバイザー協会 会員)